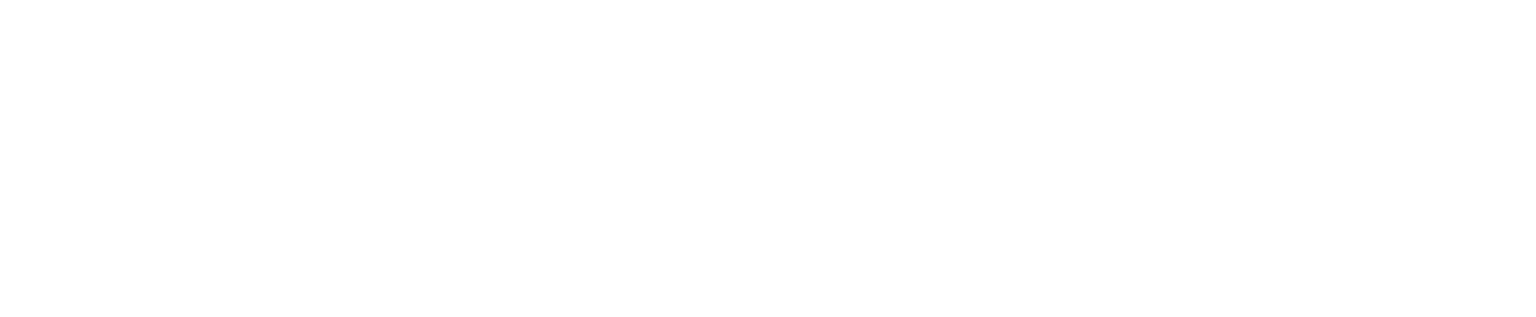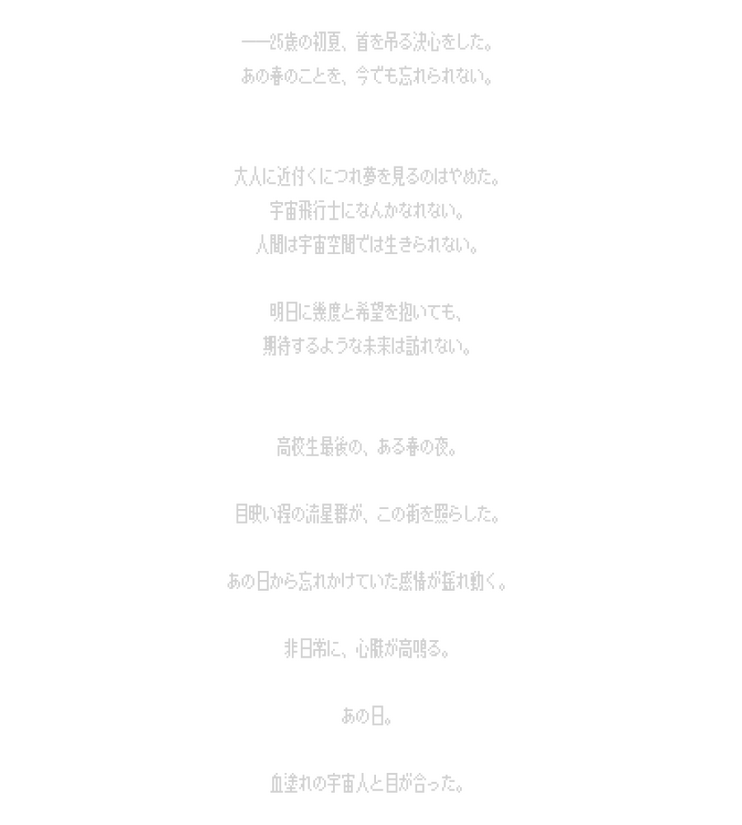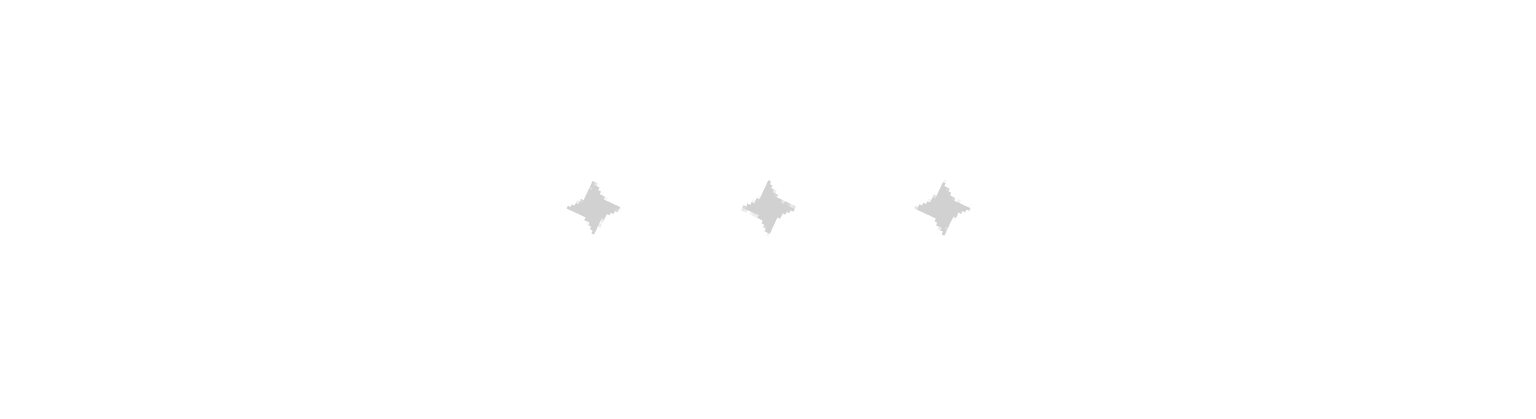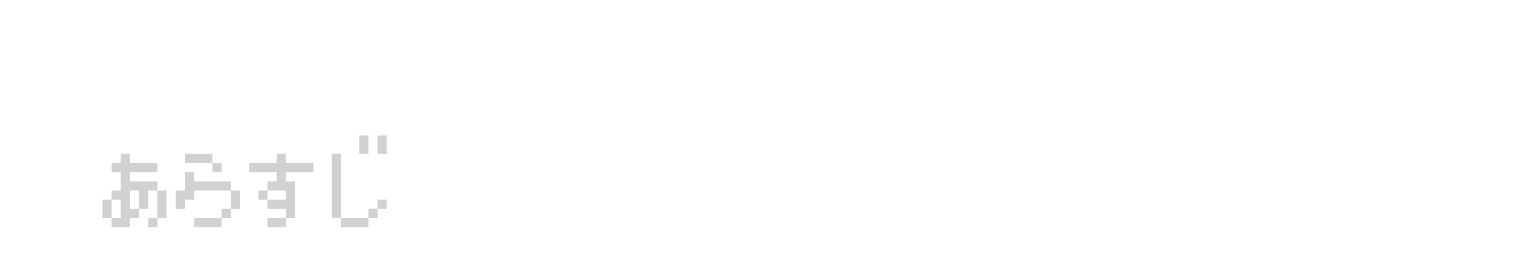谿コ縺吶°繧
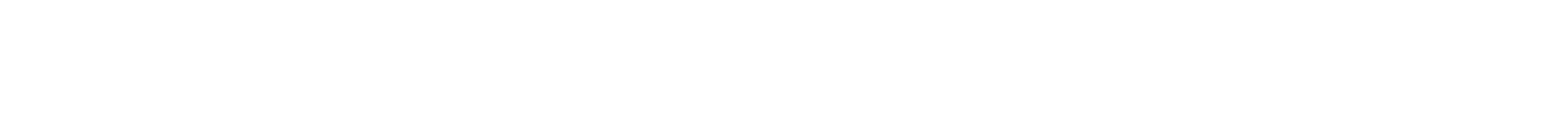
ずっと待ってたよ。あなたが今一人で寂しい思いをしているんじゃないかって、ずっと心配だったんだよ。大丈夫、あなたを一人にしないよ。だから早く会いたいの。今どこにいるの。今までどこにいたの。起きてる時も、寝る時もずっとあなたのこと考えてた。あなたに会えること。ずっと待ってたよ。あなたが今一人で寂しい思いをしているんじゃないかって、ずっと心配だったんだよ。大丈夫、あなたを一人にしないよ。だから早く会いたいの。今どこにいるの。今までどこにいたの。起きてる時も、寝る時もずっとあなたのこと考えてた。あなたに会えること。

会いたかったよ。

▲ Touch here.
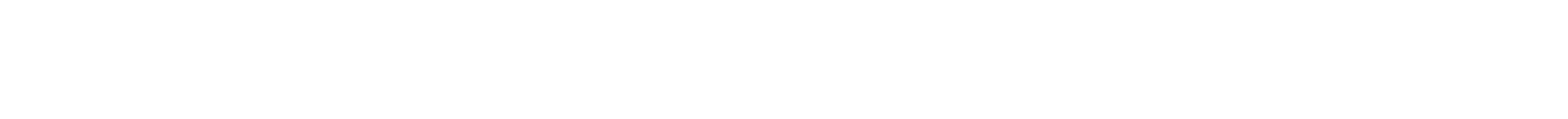
寂しくないよ、大丈夫だよ。また会えるって信じてたよ。この日をずっと待ち望んでたの。苦しいのも楽しいのも悲しいのも全部半分こしよう。それからいっぱい思い出を作ろう。それを無くさないように二人で大切にしよう。これから先も何があってもずっと一緒にいよう。寂しくないよ、大丈夫だよ。また会えるって信じてたよ。この日をずっと待ち望んでたの。苦しいのも楽しいのも悲しいのも全部半分こしよう。それからいっぱい思い出を作ろう。それを無くさないように二人で大切にしよう。これから先も何があってもずっと一緒にいよう。